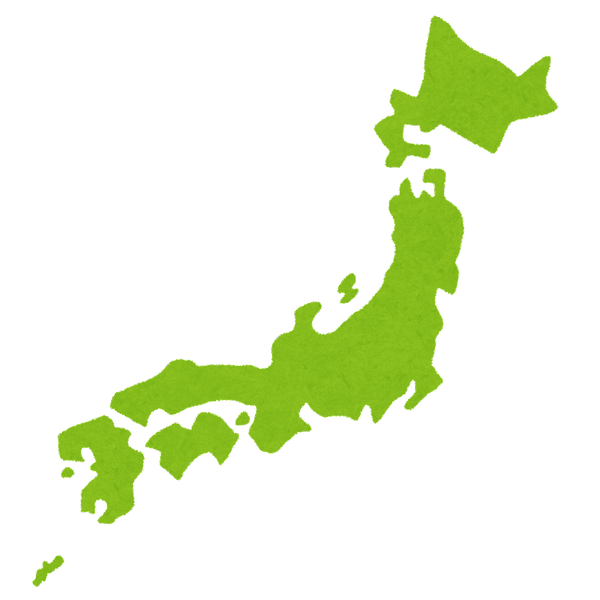著者はいずれも経済ジャーナリストや経済評論家、経済学者など。
今や「ジャパン・アズ・ナンバーワン」だった時代は遠い昔の話になった。経済は伸び悩み、給料もほとんど上がらない状態が続く。
コロナ・ワクチン開発でも欧米や中国に大きく遅れただけに、反響があるようだ。
■賃金も安い国
『安いニッポン――「価格」が示す停滞』(日経新聞出版、2021年3月刊)は日経新聞連載をもとに書籍化している。
日本の物価が世界的にみて安いということを強調すると同時に「日本の初任給はスイスの3分の1以下」「日本の30歳代IT人材の年収はアメリカの半額以下」など、
日本が賃金でも安い国になっていることを教える。経済に詳しい日経新聞の指摘だけにインパクトがあり、他メディアで紹介される機会も多い。
アマゾンの「企業・経営」部門1位。すでに6刷7万部を突破している。
同じような視点で日本を分析した本に、経済評論家、加谷珪一さんの一連の著作がある。
『日本はもはや「後進国」』(秀和システム、2019年12月刊)、『貧乏国ニッポン――ますます転落する国でどう生きるか』 (幻冬舎、20年5月刊)、
『日本は小国になるが、それは絶望ではない』(KADOKAWA、20年10月刊)と続く。
今や日本は「後進国」「貧乏国」「小国」であり、そのことを自覚してどう生きるかということを問いかけている。
「1989年に1位だった世界競争力ランキング、2019年は30位」などデータも豊富。著者は日経BP記者を経て、ファンド運用会社で投資業務なども経験している。経済の実態に明るいので説得力がある。
■「規制緩和」が拍車
日本はいつからダメになったのだろうか。そのことをテーマにしているのが経済評論家、森永卓郎さんの『なぜ日本だけが成長できないのか』(角川新書、18年12月刊)だ。
森永さんによれば、「日米同盟」の名のもとに、長い時間をかけて日本は米国に叩き売られてきたのだという。
世界のGDP(国内総生産)に占める日本のシェアは、1995年には17.5%に達していた。しかし、その後は転落を続ける。2010年には8.6%、16年には6.5%まで落ち込んだ。
この日本空洞化は3段階で進み、最終段階の「規制緩和」が拍車をかけたと見る。森永さんはテレビで見ている限り温和な印象だが、本書はなかなか手厳しい。
著名な経済学者、野口悠紀雄さんの『平成はなぜ失敗したのか』(幻冬舎、19年2月刊)も同じような視点に立つ。
平成は、日本経済にとって「失われた30年」だったと分析。それも、「努力したけど取り残された」ではなく「大きな変化が起きていることに気づかなかったために取り残された」と見る。
経済学者、金子勝さんの『平成経済 衰退の本質』(岩波新書、19年4月刊)も、衰退の源流を平成、さらにはそれ以前の「日米半導体交渉」にまでさかのぼっている。
金子さんは10年に、児玉龍彦・東京大学先端科学技術研究センター名誉教授と共著『新興衰退国ニッポン』 (現代プレミアブック)を出版、早々と「日本の衰退」を指摘している。
児玉さんはコロナ問題の論客としてテレビで見かける機会も多い。
(以下略、全文はソースにて
https://www.j-cast.com/trend/2021/09/11419967.html?p=all
関連記事
日本礼賛ブームのなぞ(2018年5月30日)
「日本礼賛本」がベストセラーになり、テレビでは外国人が日本を褒め称える番組が数多く放送されている。
ネットの世界では「中国人が日本の美点を紹介した」情報が大人気。まるで日本礼賛ブームといえる状況だ。
https://str.toyokeizai.net/books/9784492918982/
「日本すごいブーム」とトランプ現象から学ぶべきことがある(2020年12月14日)
第2次安倍政権の発足後、この流れに一部の放送局や出版社がビジネス目的で便乗すると、嫌韓や反中を含んだ「日本すごい論」が盛り上がり、
右派にとって不都合な事実は徹底的に叩き潰(つぶ)すネット右派層がアクティブ化していったように思います。
https://wpb.shueisha.co.jp/news/politics/2020/12/14/112633/
続きを読む
Source: エクサワロス